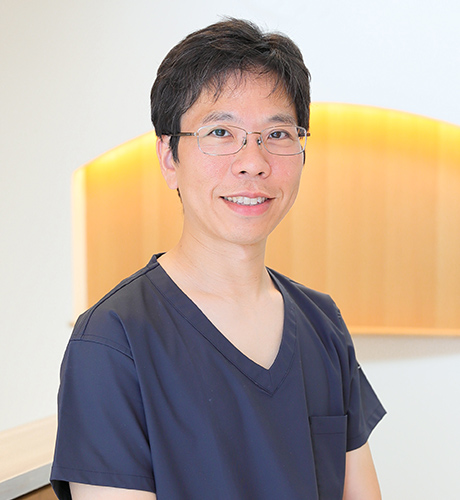こんにちは。こばやし矯正歯科です。
目立たない矯正装置として注目されているマウスピース矯正(インビザライン)ですが、なぜマウスピースで歯が動くの?と疑問に感じられている方もいらっしゃるかもしれません。
マウスピース矯正による歯の移動は、歯の根元周りに存在する組織が重要な役割を果たしています。
今回は、マウスピース矯正の仕組みや治療の流れについて詳しく解説していきます。
目次
■歯列矯正で歯が動く仕組み
歯が動く仕組みの中心は、歯根(歯の根元部分)と歯槽骨(歯根を支える骨)の間にある歯根膜にあります。
-
マウスピースで歯に矯正力をかけると歯根膜が反応し、骨をつくる「骨芽細胞」と骨を溶かす「破骨細胞」が活性化する
-
歯に矯正力が加わると、歯根は力をかけられた方向に引っ張られる
-
圧迫された側の歯根膜では「破骨細胞」が働き、歯を支えている骨を溶かして歯が移動するスペースを作る
-
「3」のスペースに歯が移動すると、反対側の歯根膜では「骨芽細胞」が働き、新しく骨を形成する
上記の骨吸収と骨形成のプロセスが繰り返されることで、少しずつ歯が動いていきます。
マウスピース矯正の場合は、患者さま自身で交換していく複数のマウスピースが少しずつ形の異なる設計になっています。指示された期間に応じて新しいマウスピースに交換することで、歯を徐々に理想の位置へ導いていきます。
■マウスピース矯正(インビザライン)の一般的な流れ
次に、実際のマウスピース矯正の流れについて見ていきましょう。
◎精密検査を受ける
まず、基本的な歯科検査に加え、セファロレントゲンやCT検査で歯並びと歯の形状を詳細に確認します。口腔内スキャナー(iTero)などで歯の型取りも行い、正確なデータを収集します。
また、治療内容や検査でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
◎治療計画
精密検査の結果をもとに、正しい噛み合わせや歯並びに導くための治療計画を立てます。矯正後の歯並びもシミュレーションで確認することができますので、患者さまにご納得いただいた状態で矯正治療を進めていきます。
◎マウスピースの作成
収集したデータをもとに、患者さんの口腔状態に合わせた複数のマウスピースが作成されます。
◎マウスピースを装着・交換する
患者さんは日常生活でマウスピースを装着します。マウスピースは1日20時間以上(食事と歯磨き以外の時間)の装着が推奨されています。治療の進行に合わせて定期的に新しいマウスピースに交換していき、通院頻度は患者さまによって異なりますが、2ヵ月に1回は歯科医院での経過観察も行います。
※公益社団法人 日本矯正歯科学会:
『アライナー型矯正装置による治療指針』
◎保定装置を装着する
矯正治療の完了後、リテーナーと呼ばれる保定装置を装着し、整った歯並びの後戻りを防ぎます。その後も定期的なメンテナンスなどの通院により、長期的な歯並びの維持を図ります。
■マウスピース矯正ができない歯並びはあるの?
現在のインビザラインは捻転や八重歯の矯正などにも適応され、ほとんどの動きに対応しています。しかし、埋伏している歯を引っ張るような場合は歯を動かしにくい可能性があります。その際はワイヤー矯正など、ほかの治療法が選択されることもあります。
また、顎変形症のように上下の顎の大きさやずれ、形の違いで噛み合わせのバランスに異常があり、手術が必要になるような症例では、マウスピース矯正では適応できません。
■まとめ
マウスピース矯正では、歯の根元にある「歯根膜」という組織のはたらきによって歯が少しずつ動いていきます。複数のマウスピースは少しずつ形状が異なり、交換することで徐々に理想の歯並びへ歯が整っていく仕組みになっています。
こばやし矯正歯科では、経験豊富な歯科医師が一人ひとりに合わせたマウスピース矯正の治療計画を立案します。専用の歯科用CTやセファロレントゲンなどによる正確な口腔内診断にも対応していますので、マウスピース矯正に興味のある方は、ぜひご相談ください。